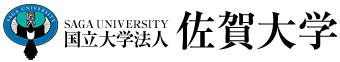血液で肺がんの遺伝子異常がわかる事を多施設共同研究で検証しました

血液で肺がんの遺伝子異常がわかる事を多施設共同研究で検証
肺がん治療で投与される分子標的薬(EGFR阻害剤)の耐性化遺伝子変異を、末梢血 5mlだけで安全に検出できる簡易迅速
検査法を開発した(世界肺がん学会誌2011年5月10日論文受理)。今回、多施設共同前向き試験でこの検査系の有用性を検
討し、確かに耐性化時に血液中で変異が検出される事、がんの進行により検出率が上昇する事を明らかにした(日本がん学会誌、
2015年11月10日論文受理)。
分子標的薬は、がん組織の遺伝子変異を検査する事で効果予測、耐性化判定が可能である。しかし、がん組織を侵襲的検査(気
管支鏡検査、手術など)で採取する必要があり、また、採取する部位により検査結果が異なる事が問題である。
我々は、血液の中に遊離している肺がん細胞由来のDNAを用いて分子標的薬であるEGFRチロシンキナーゼ阻害剤の耐性化
遺伝子T790M変異を検出する検査系を確立し2011年発表した。この度、この検査系の有用性を検証するため、兵庫県立が
んセンター根来俊一部長(化学療法担当)、佐賀大学血液・呼吸器・腫瘍内科木村晋也教授を共同研究責任者として多施設共同前
向き試験を実施した。
国内7施設が参加し、EGFRチロシンキナーゼ阻害剤投与開始から耐性化まで継時的にT790M変異のモニタリングを行っ
た。多くは耐性化時に変異が検出され、がんの進行に伴い検出率が上昇する事を明らかにした。また、肺以外に転移した場合検出
率が上がり、予後が悪い事がわかった。この事から、血液に遊離している肺がん細胞由来のDNAは転移を反映していることが示
唆された。この研究の中で、検査のための、がん組織採取(再生検)は14%しか施行されず、その困難さが浮き彫りになった。
T790M阻害剤が近々上市予定である。本技術を用いて、安全に治療効果を予測できれば、個々の患者に合った治療の選択を
行う事ができる。
検査系は極めて簡便であるため病院内での検査が可能であり、速やかに検査結果を入手し、次治療の選択ができる。
【お問い合わせ先】
佐賀大学医学部 血液・呼吸器・腫瘍内科 診療教授 荒金尚子 0952-34-2356
血液・呼吸器・腫瘍内科 教授 木村晋也 0952-34-2353