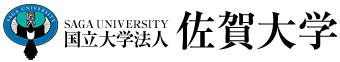心不全患者における遠隔モニタリングの高次脳機能に対する有効性とその意義を解明

【研究者】
代表者:金子哲也、田中敦史、野出孝一
分担者や協力者:高守史子、本郷 玄、坂本佳子、矢島あゆむ、浅香真知子、安心院法樹、神下耕平、井上洋平、長友大輔、
藤松大輔、琴岡憲彦
【研究成果の概要】
心不全は「心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気」とされています。悪化によりしばしば入院を要することがあり、そのたびに心不全は悪化の一途を辿ります。今後、高齢化および心不全患者の更なる増加が予想される中で、いかに心不全の悪化を予防していくかが重要とされています。
本研究(S-HOMES試験)では、心不全患者計41名(平均年齢64.8±13.8歳、男性68.3%)に対して、IoTを用いた遠隔モニタリングを実施し、その臨床的効果を検証しました。本研究で用いられた遠隔モニタリングシステムでは、患者自身が血圧や心拍数、体重を毎日測定し、その結果が自動的に当院へ遠隔データとしてアップされます。そのデータを選任の看護師が確認し、既定の閾値を超えた場合に担当医に知らせ、担当医から患者やその家族らへ連絡を行い、状態の確認や受診勧奨といったコーチングからなるケアサイクルを実施しました。その結果、12か月の観察において心不全症状の改善と同時に、高次脳機能の一つである実行機能の指標とされるTrail Making Test Part B(TMT-B)スコアが有意に改善していることが明らかになりました。また、中央値20.5ヵ月の追跡期間中、実行機能障害を有する患者における心不全よる入院の発生率は、実行機能障害を有さない患者よりも有意に高率であることも判明しました。さらに、認知機能障害を有さない患者群においても同様の結果であり、実行機能が心不全患者において予後を規定する因子である可能性が考えられました。
以上より、遠隔モニタリングは、心不全患者の実行機能の改善に有効であり、実行機能の改善へ向けた支持療法が心不全患者の予後改善につながることが示唆されました。
【研究成果の公表媒体(論文や学会など)】
論文:Hypertension research誌 2025年4月25日 英国時間午前1時
学会:第46回 日本高血圧学会総会 2024年10月12~14日
【今後の展開】
本研究から、遠隔モニタリングをうまく使うことができれば、特に高齢心不全患者における実行機能改善などを通じて、心不全の悪化による予定外の入院リスクを抑制できる可能性が示唆されました。そこで、今後の課題として、遠隔モニタリング体制や管理法は未だ世界的にも検討段階であり、より精度の高い遠隔モニタリングシステムの構築とその有効性に対する詳細な評価が必要とされています。また、本研究で示唆されたように、実行機能の改善に資するより適切な支持療法の開発や臨床応用についてもさらに検討していく必要があると考えています。
【その他PRしたい特記事項】
高次脳機能の一つである実行機能は、心不全患者の自己管理において重要な能力と思われます。しかし、心不全患者に対する実行機能についての研究は乏しいのが現状です。そのため、本研究から得られた知見は、心不全と実行機能との関連およびその臨床的意義を紐解く上で重要な知見をもたらすものと考えています。
【本件に関する問い合わせ先】
研究代表者:金子哲也、田中敦史、野出孝一
所属:佐賀大学 循環器内科
電話:0952-34-2364
FAX: 0952-34-2089
Email: sh2699@cc.saga-u.ac.jp (金子哲也)、tanakaa2@cc.saga-u.ac.jp (田中敦史)、node@cc.saga-u.ac.jp (野出孝一)