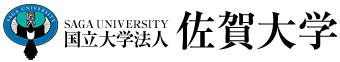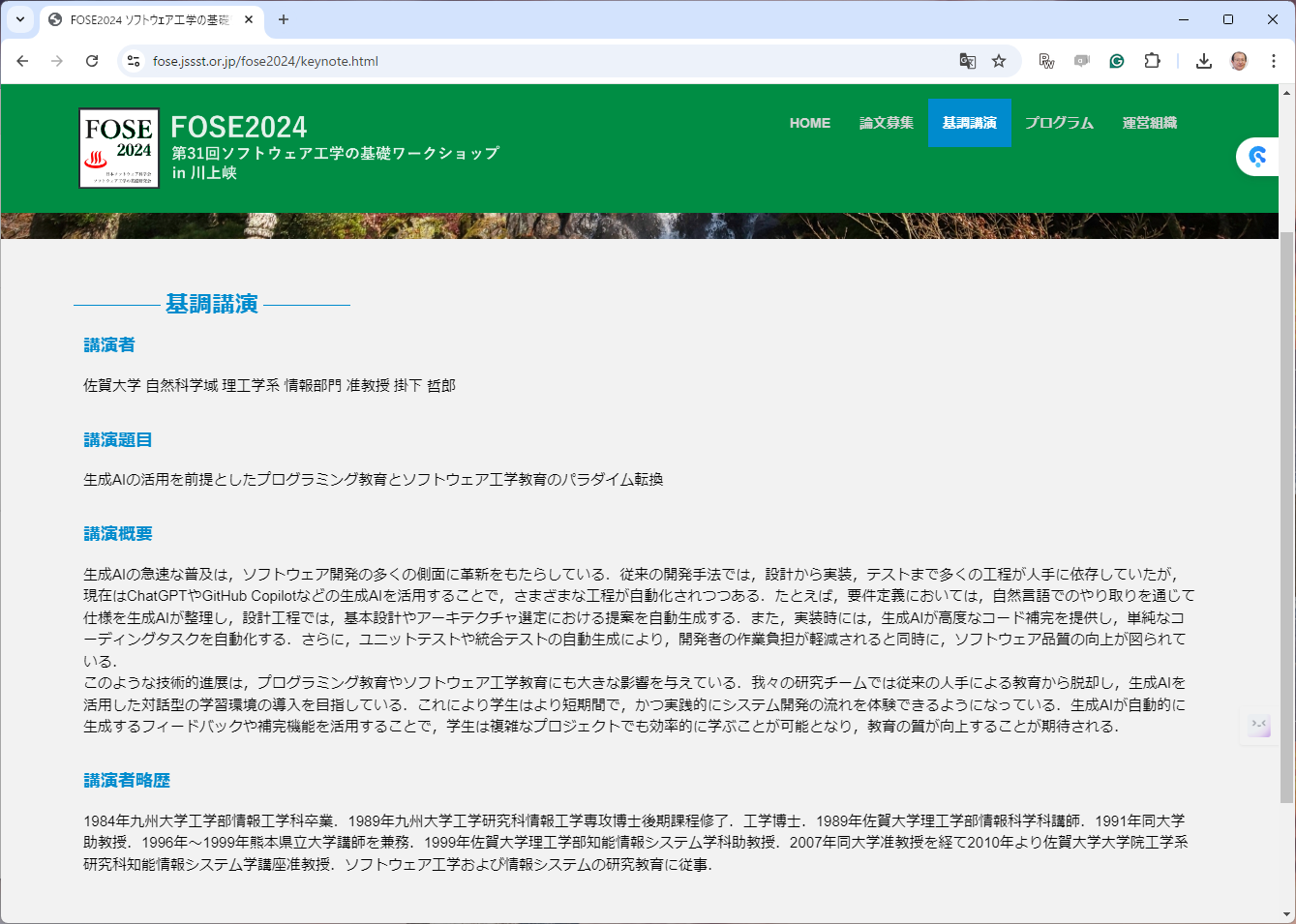理工学部数理・情報部門の掛下 哲郎 准教授が第31回ソフトウェア工学の基礎ワークショップ(FOSE2024)にて生成AIによる情報教育のパラダイム転換について基調講演を行います。

【概要】
理工学部 数理・情報部門の掛下 哲郎 准教授が、2024年11月28日(木)~30日(土)に佐賀市のホテル龍登園にて開催される第31回ソフトウェア工学の基礎ワークショップ(FOSE2024)にて「生成AIの活用を前提としたプログラミング教育とソフトウェア工学教育のパラダイム転換」と題した基調講演を行います。
【本文】
2024年11月28日(木)~30日(土)に佐賀市のホテル龍登園にて開催される第31回ソフトウェア工学の基礎ワークショップ(FOSE2024)において、理工学部 数理・情報部門の掛下 哲郎 准教授が基調講演を行います。本講演では、掛下准教授らの研究チームが取り組んでいる科研費・基盤研究(C)「生成AIによるプログラミング教育のパラダイム転換と教育支援ツールの研究開発」および「生成AIによるシステム開発の自動化を前提としたソフトウェア工学教育の再構築と実践」の成果を踏まえて、生成AIによるソフトウェア工学へのインパクトの他、プログラミング教育やソフトウェア工学教育に求められるパラダイム転換について最新動向を踏まえた考察を紹介します。
記
主 催 :日本ソフトウェア科学会 ソフトウェア工学の基礎研究会
イベント名 :第31回ソフトウェア工学の基礎ワークショップ(FOSE2024)
講演題目 :生成AIの活用を前提としたプログラミング教育とソフトウェア工学教育のパラダイム転換
講 演 者 :理工学部 数理・情報部門 掛下 哲郎 准教授
日 時 :2024年11月29日(金)9:00~10:30
場 所 :ホテル龍登園(佐賀市大和町大字梅野120)
講演内容 :
生成AIの急速な普及は、ソフトウェア開発の多くの側面に革新をもたらしている。従来の開発手法では、設計から実装、テストまで多くの工程が人手に依存していたが、現在はChatGPTやGitHub Copilotなどの生成AIを活用することで、さまざまな工程が自動化されつつある。たとえば、要件定義においては、自然言語でのやり取りを通じて仕様を生成AIが整理し、設計工程では、基本設計やアーキテクチャ選定における提案を自動生成する。また、実装時には、生成AIが高度なコード補完を提供し、単純なコーディングタスクを自動化する。さらに、ユニットテストや統合テストの自動生成により、開発者の作業負担が軽減されると同時に、ソフトウェア品質の向上が図られている。
このような技術的進展は、プログラミング教育やソフトウェア工学教育にも大きな影響を与えている。我々の研究チームでは従来の人手による教育から脱却し、生成AIを活用した対話型の学習環境の導入を目指している。これにより学生はより短期間で、かつ実践的にシステム開発の流れを体験できるようになっている。生成AIが自動的に生成するフィードバックや補完機能を活用することで、学生は複雑なプロジェクトでも効率的に学ぶことが可能となり、教育の質が向上することが期待される。
イベントホームページ:https://fose.jssst.or.jp/fose2024/keynote.html
イベントのホームページ
以上
【本件に関する問い合わせ先】
掛下 哲郎 准教授(kake@cc.saga-u.ac.jp)